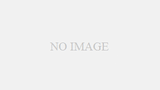二つの宗教が混在する街、ミンダナオ島のイリガン市に暮らす人びとの「消えない差異と生きる」日常について。物語スタイルの記述で、人びとの暮らしや葛藤を活き活きと描き出していて、まるで映画のようです。ただ同時に、分断社会の民主主義や平和構築といったテーマにも重い課題を投げかけているように思います。
本書によると、イリガン市の日常は、複数の民族や宗教間の不信や無理解をも包み込んだ「共存」で成り立っているそうです。しかし、国家やNGOの和平のアプローチは、二つの宗教の間に明確な境界線を引こうとするので、この微妙なバランスで成り立っている「共存」を脅かしてしまったり、看過してしまうといいます。
たとえば、前アキノ政権は念願の和平を進めるべく、イスラーム教徒の自治政府設立を進めましたが、逆説的にも相互不信が高まり、暴力を誘発してしまいました。他方、NGOや大学は、理想的なイスラーム教徒と理想的なキリスト教徒の共存を説くけれども、人々の暮らしの実態からはかけ離れているといいます。
本書はこうしたアプローチの限界を指摘しつつ、ミンダナオの人々が実践してきた「きれいごとじゃない日常が作る平和」にもっと目を向けるよう促します。二つの宗教を超えた恋愛や結婚もあるし、そこから生まれる子供たちもいる。真面目なキリスト教徒が信仰を突き詰めた結果、イスラーム教徒に改宗することだって盛んになっている、というのです。
もちろん、宗教の境界線を越えたといっても、完全な調和が達成されるわけではありません。むしろ家族やコミュニティのなかに複数の宗教が入ることによって、反目や葛藤も生じます。でも、それでも家族や隣人として一緒に暮らし続けていく。そんな「決して消えない差異を内包した共存」があるというのです。
ただ昨年には、イリガン市のすぐ隣にあるマラウィ市で大きな戦闘があったように、そんな微妙なバランスで成り立ってきた「共存」も壊れつつあるのかもしれません。そんな時に、政策レベルで人びとの日々の共存を活かした和平というものをどのように構想できるのでしょうか。政策は、どうしても「誰か」ではなく、「何か」という集合で人びとを捉えてしまうので、なかなか難しいですよね。